自主的に参加する子供学級。
地域の方や先生方と、色々な体験をさせてくれます。
今回はそこで長女ちゃんが門松を作りました。
こども楽級(がっきゅう)
以前、イッサンもボランティアで参加してきました。
その際はスポーツをしたのですが、子供達と一緒に体を動かすのは楽しいですね(^^)
その時の記事がこちらになります↓↓

この時はスポーツでしたが、主に公民館で物作りが多いのかな?
去年なんかは手話の勉強なんかもやってました。
とても良い取り組みだと思います(^^)
門松
お正月に家の門の前に飾られる門松。
どんな意味があるのでしょうか?
ちょっと調べてみました。
門松 正月に家の門の前などに立てられる松や竹を用いた正月飾り。松飾り、飾り松、立て松とも言う。新年の季語。古くは、木のこずえに神が宿ると考えられていたことから、門松は年神を家に迎え入れるための依り代という意味合いがある。 ~Wikipedia~
家の門の前に飾ることによって、年神さまが来て下さると言うありがたい飾り。
この様な意味なども子供学級では教えて下さるので、子供たちもとてもいい勉強になりますよね(^^)
さて、長女ちゃんの作った門松はどんな飾りになっているのでしょうか?
長女ちゃん作
こちらが長女ちゃんの作った門松になります。

じゃじゃん!
本格的で立派な門松です!
凄く良いものが作れたのではないでしょうか(^^)
記念に長女ちゃんと門松をパシャリ。

大きさも分かると思いますが、まぁまぁ良いサイズです。
飾るのが楽しみです(^^)
いつ飾るの?
早いところでは12月13日から飾るそうですが、一般的には12月28日から飾り付けるそうです。
もし、12月28日を逃した方は、12月30日に飾りましょう。
注意して頂きたいのが、お飾りなどを飾ってはいけない日があると言うこと。
それは、12月29日と12月31日。
なぜ飾ってはいけないかを説明いたします。
12月29日に飾るのは、「苦立て(二重苦)」で縁起が悪いと言う事だそうです。
12月31日は、「一日飾り」と言って、お通夜飾りに似て、神様に失礼に当たると言われています。
ですので、決して12月29日と31日にはお飾りや門松を飾らないように注意しましょう!

いつ片付ける?
お飾りや門松を飾るのは、一般的に1月7日までと言われています。
1月7日までは、「松の内(神様のいる期間)」と呼ばれていて、新年のご挨拶などが行われるこの日までは飾っておきましょう。
地域によっては1月15日(小正月)まで飾るところもあるそうです。
今ではお飾りをしない家も多いと思いますが、こう言った行事は大切にしたいですね。
年神さまを招いて、新年も良い年にしたいですしね(^^)
〆
今年は長女ちゃんのおかげで、初めて門松を飾ります。
飾る日にちを間違えない様に。
来年も良い年にしたいですね(^^)
皆さんのお家は、お飾りや門松を飾りますか?
飾っていないお家も、今年は飾ってみてはいかがでしょうか?
皆さんも、年神さまを招いて良い年にしましょう。
本日はこの辺で。


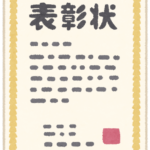
コメント