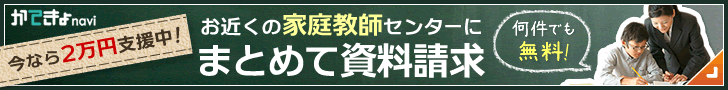
3学期も終わりに近づいている今日このごろ。
最近の次女ちゃんの様子です。
登校
毎日、行き渋ることもなく笑顔で行ってます。ママに車で送ってもらって(笑)
未だ、班登校は出来ず。
それでも、去年とは違い、学校に到着してからママと離れる際に泣くことは無くなりました。
徐々に成長しております。

学校での様子
あれ以来、教室には1日1時間くらいしか入れてません。
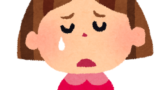
だいたい5時間目とか6時間目に教室に入るくらいで、その他の時間は、保健室の隣にある相談室に。
そこで、持参したドリルや、出られてない授業のプリントやテストをして過ごしています。
相談室には他にも、次女ちゃんと同じく教室に入れない別学年の子が2人いますが、その子たちは次女ちゃんとは違った理由で教室に入れないようです。
次女ちゃんは、その別学年の男の子が面白くて好きなようで、「今日〇〇君休んでた~」とか、「今日〇〇君、こんな面白いこと言ってた~」と話してくれます。
相談室が居心地良さそうなそんな感じ。
欲を言えば、2学期の時のようにもっと教室に入ってもらいたいな。
無理をさせてはいけないとのことで、「特に父親は優しくあるべき」と病院の先生から助言を頂いてからは、次女ちゃんの背中を押すこともなく過ごしています。
その分、奥様には負担が掛かっている状態です。
特に奥様は焦りの気持ちが大きく、未来のことを沢山心配している様子。
先の分からないことを考えても取り越し苦労であることを伝えても、やはりそういう性分なのでしょう、思い悩むことがあるみたいです。
影響の輪の外側
しかし、奥様がいくら悩もうが、教室に入るか入らないかは次女ちゃんが決めること。
奥様が影響を与えることができる範囲外のことなのです。
まさに、この話がそれだと思います。
ある青年が馬に水を飲ませようと湖まで行きましたが、馬は水を飲もうとしませんでした。
要するにこの話は、「水を飲むか飲まないかを決めるのは馬であり青年ではない」と言うことが書かれています。
馬は青年の影響の輪の外側だったと言うことなんですね。
この話で言う「青年」は奥様で、「馬」が次女ちゃん。
奥様は次女ちゃんに教室に入ってほしいから学校に連れて行くけど、次女ちゃんは思うように教室に入ってくれない。
そこを悩んでいても仕方がなく、何か次女ちゃんにアプローチ出来るのなら、次女ちゃん本人の症状である場面緘黙や母子分離不安が緩和されるようなことをするのが良いのだと考えます。
良書
そこまで分かっているのですが、なかなか最善策が出てこないのが困りどころ。
その為に、先ずは症状に対しての理解を深めることが大切なので、色々な本を読みました。
その中でも、この「子どもの場面緘黙サポートガイド」という本が良かったです。
場面緘黙の子どもに対して、どの様に接したらよいのかが具体的に書かれており、どちらかと言うと小学校の先生向けに書かれた本だったので、もう一冊購入して小学校に寄付しました。
子供さんの場面緘黙で悩んでいる方は、先ず、理解することから始めてみて下さい。
その際、この本が凄く役に立つと思います。
〆
3学期はこんな調子で終わると思います。
新学年からは担任の先生も変わりますので、慣れるまでは教室に入れないかも知れません。
春からもう少し我慢の日々が続きます。
それまでも、次女ちゃんの症状に良い影響を与えられる何かを得るため、我々親も勉強です。
同じようなことで悩んでいらっしゃる方に、少しでも共感や勇気を与えられたらと思います。
思い悩み過ぎて周りが見えなくなる時こそ、しっかり視野を広げていきましょう!
本日はこの辺で。
~・~・~・~・~・~・
家庭教師選びに困ったらこちら!
東証一部上場企業が運営!
利用者4万人以上!
厳選の37社から選べる!
それが【かてきょナビ】!
気になる方は覗いて見てくださいね(^^)↓↓
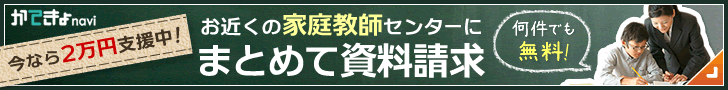

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20d20119.d24d8c81.20d2011a.fe67b2ad/?me_id=1213310&item_id=19385737&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3743%2F9784772613743.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


コメント